科目解説書●石原ゼミ
石原ゼミ
進級/卒業制作
http://www.infonet.co.jp/apt/March/syllabus/Isihara/dissertation.html
石原ゼミでは、科目[卒業研究]/[ゼミナール]の成績は、制作(発表を含む)と輪講での成果を総合して評価します。そのうえで、1年間の専門的な学習を完成したというしるしとして、きみたちは年度の最後に進級/卒業制作を提出しなければなりません。進級/卒業制作を提出しなければ、学習に対する評価に関わりなく、単位は認められません。
進級/卒業制作は、ゼミの規定(提出準備面接から確認までにかけて少しずつ説明します)にしたがって提出しなさい。決められた手続きにしたがって成果が提出されなかった場合は、それまでに設計制作してきた作品の内容や発表での評価はみんな無効になります。
進級/卒業制作は、その年度にA/B/C作品として制作された作品のうちのどれか一つをベースにして、それをさらに秀れた作品に作り直す作業を経たものでなければなりません。
成績の問題はさて置いて、進級/卒業制作は、きみたちの一生にとって、最も重要な作品になるはずです。なぜかと言うと、それは、きみたち(のほとんど)にとって、初めての受賞作品(卒業認定という賞がもらえるわけだから)になるからです。
きみたちはこれから、作家やデザイナーとして就職したり、コンクールに応募したり、個展の会場を借りたりする時に、自分の作家となりを示すために、業績書を見せなければならなくなります。(もっといい作品が作れるようになるまで)進級/卒業制作は、その最初に書く作品になります。
進級/卒業制作は、いつものレポートや課題とは全く格が違う仕事になります。このことをしっかり胆に銘じて取り組んでいくようにしてください。
石原ゼミでは、進級/卒業制作は次の手順を経て提出することになります。
進級/卒業制作は、ゼミの規定(提出準備面接から確認までにかけて少しずつ説明します)にしたがって提出しなさい。決められた手続きにしたがって成果が提出されなかった場合は、それまでに設計制作してきた作品の内容や発表での評価はみんな無効になります。
進級/卒業制作は、その年度にA/B/C作品として制作された作品のうちのどれか一つをベースにして、それをさらに秀れた作品に作り直す作業を経たものでなければなりません。
成績の問題はさて置いて、進級/卒業制作は、きみたちの一生にとって、最も重要な作品になるはずです。なぜかと言うと、それは、きみたち(のほとんど)にとって、初めての受賞作品(卒業認定という賞がもらえるわけだから)になるからです。
きみたちはこれから、作家やデザイナーとして就職したり、コンクールに応募したり、個展の会場を借りたりする時に、自分の作家となりを示すために、業績書を見せなければならなくなります。(もっといい作品が作れるようになるまで)進級/卒業制作は、その最初に書く作品になります。
進級/卒業制作は、いつものレポートや課題とは全く格が違う仕事になります。このことをしっかり胆に銘じて取り組んでいくようにしてください。
石原ゼミでは、進級/卒業制作は次の手順を経て提出することになります。
提出準備面接
| 日時 |
12月上旬 このあとすぐに完成作業にとりかからないといけないので、なるべく最初の週にはすませておこう |
| 会場 |
石原研究室 |
| 持ってくるもの |
A作品 B作品 (大きい場合はポートフォリオ) 発表を証明する書類と記録 |
ここでは、次の四つのことを行なう。
○ベースにする作品をどちらにするか決める
初めに説明したように、進級/卒業制作はその年度にA/B/C作品として制作された作品のうちのどちらかをベースにしなければなりません。つまり、ほかの学生や先生が知らない全く新しい作品を進級/卒業制作として提出することはできない。
したがって、A/B/C作品のあとで制作して合評会でも発表したことがある作品なら、場合によってはベースにすることができる。また、最悪の事態と言っていいけれど、卒業制作については、進級制作として提出しなかった方の作品が今年度のA作品/ B作品よりも秀れている場合は、それをベースとして選ぶこともあるかもしれません。
○提出するまでにどこをどう直すか決める
A/B/C作品をそのまま提出しただけでは、進級/卒業制作としては認められない。
どんな場合でも言えることだけれど、何かを表現するうえで最も重要なことは、もっといい表現を実現するということについてどこまで強いこだわりを持ち続けるかということです。進級/卒業制作では、そこをぜひ確かめたい(だから新作を提出することを認めていない)。それに、成績ということを考えると、直す前の状態での評価はもう春に確定している。
直すと言っても、その手段は素材の交替、構成の変更、または同一の企画による完全な再制作などいろいろです。それもここで決めておく。
○提出するものの内容と形式を決める
あらかじめ何をどう提出するか決めておく。
作品の形式によっては、作品そのものを提出することができない場合もある。また、どんな個展を開いたかとか、どんなコンクールでどんな評価を受けたかとかいった、ポートフォリオも作品の大切な一部です。
作品のほかには、個展やコンクールの趣意書、会場の記録(個展)、応募書の写しや審査報告書(コンクール)、操作説明書などが必要になるだろう。
・ビデオ作品はミニDVに正規の作品として通用する形式で収録する
・コンピュータ作品はMOなどのメディアに収録し、起動ファイルを明らかにしておく
○ゼミ専用提出ケースを受け取る
進級/卒業制作は、紙に印刷した論文とは違って細かかったりかさばったりするので、専用の提出用ケースに入れて提出します。卒業制作の場合は、窓口でそれをさらに封筒に入れてもらうことになります。
そのためのケースと、論文で言えば表紙に当たる表書き用紙を渡す。
最終面接を済ませていないと卒業成果を提出することはできない。
○ベースにする作品をどちらにするか決める
初めに説明したように、進級/卒業制作はその年度にA/B/C作品として制作された作品のうちのどちらかをベースにしなければなりません。つまり、ほかの学生や先生が知らない全く新しい作品を進級/卒業制作として提出することはできない。
したがって、A/B/C作品のあとで制作して合評会でも発表したことがある作品なら、場合によってはベースにすることができる。また、最悪の事態と言っていいけれど、卒業制作については、進級制作として提出しなかった方の作品が今年度のA作品/ B作品よりも秀れている場合は、それをベースとして選ぶこともあるかもしれません。
Q
A/B/C作品のどれかを直すのではなく、同じテーマで全く新しく作り直して提出したいんですが、かまいませんか?
(06-01-06 匿名希望さん)
A 原則としてはかまいません。
ただ、新しく作り始めたりして間に合うのか(手抜きで作って間に合せても意味がないし)確認したいので、香盤表などをきちんと作ってから相談に来てください。無理がないことが分かったら進級/卒業制作として正式に認めます。
(06-01-06 匿名希望さん)
A 原則としてはかまいません。
ただ、新しく作り始めたりして間に合うのか(手抜きで作って間に合せても意味がないし)確認したいので、香盤表などをきちんと作ってから相談に来てください。無理がないことが分かったら進級/卒業制作として正式に認めます。
○提出するまでにどこをどう直すか決める
A/B/C作品をそのまま提出しただけでは、進級/卒業制作としては認められない。
どんな場合でも言えることだけれど、何かを表現するうえで最も重要なことは、もっといい表現を実現するということについてどこまで強いこだわりを持ち続けるかということです。進級/卒業制作では、そこをぜひ確かめたい(だから新作を提出することを認めていない)。それに、成績ということを考えると、直す前の状態での評価はもう春に確定している。
直すと言っても、その手段は素材の交替、構成の変更、または同一の企画による完全な再制作などいろいろです。それもここで決めておく。
○提出するものの内容と形式を決める
あらかじめ何をどう提出するか決めておく。
作品の形式によっては、作品そのものを提出することができない場合もある。また、どんな個展を開いたかとか、どんなコンクールでどんな評価を受けたかとかいった、ポートフォリオも作品の大切な一部です。
作品のほかには、個展やコンクールの趣意書、会場の記録(個展)、応募書の写しや審査報告書(コンクール)、操作説明書などが必要になるだろう。
・ビデオ作品はミニDVに正規の作品として通用する形式で収録する
・コンピュータ作品はMOなどのメディアに収録し、起動ファイルを明らかにしておく
○ゼミ専用提出ケースを受け取る
進級/卒業制作は、紙に印刷した論文とは違って細かかったりかさばったりするので、専用の提出用ケースに入れて提出します。卒業制作の場合は、窓口でそれをさらに封筒に入れてもらうことになります。
そのためのケースと、論文で言えば表紙に当たる表書き用紙を渡す。
最終面接を済ませていないと卒業成果を提出することはできない。
完成作業
| 日時 |
発表
| 日時 |
Q
進級/卒業制作として指定した作品の発表についでですが、個展で発表する場合は、絶対に12月以前に開かないといけませんか?
(00-11-26、A-さん)
A いけません。
だって間に合わないから。
(00-11-26、A-さん)
A いけません。
だって間に合わないから。
Q
課題だから上映会を自分で開こうと思っています。ほかの人たちにも作品を持ち寄ってもらうつもりなんですが、その人たちも発表をしたってことになるんですか?
(00-11-16、E-くん)
A (この科目の課題に限って言うと)発表をしたことにはなりません。この場合で言うと、発表をしたと認められるのは主催者のE-くんだけです。
厳しいと思うかもしれませんが、それには理由があります。ほかの人が準備してくれた展覧会や上映会に出品しただけでは、発表の練習になりませんからです。自分で企画を立てて、会場を確保したり宣伝したりすることができるということをきちんと見せてください。
ただし、身内ではなくて、公けの団体が主催していて審査が行なわれるような上映会だったら、応募するだけでも(もちろん審査に合格してくれないと困るけど)立派な発表として認められます。
(00-11-16、E-くん)
A (この科目の課題に限って言うと)発表をしたことにはなりません。この場合で言うと、発表をしたと認められるのは主催者のE-くんだけです。
厳しいと思うかもしれませんが、それには理由があります。ほかの人が準備してくれた展覧会や上映会に出品しただけでは、発表の練習になりませんからです。自分で企画を立てて、会場を確保したり宣伝したりすることができるということをきちんと見せてください。
ただし、身内ではなくて、公けの団体が主催していて審査が行なわれるような上映会だったら、応募するだけでも(もちろん審査に合格してくれないと困るけど)立派な発表として認められます。
確認
| 日時 |
06-01-10 5/6限 |
提出するものが完全に揃ったか、先生と二人で確かめます。
ビデオならDVテープ、写真ならCD/DVDなどの媒体に記録して提出するのがふつうでしょう。この場合に、提出する作品以外のもの(=ほかの作品や作業の経過)が媒体の中に残っていてはいけません。これらはすべて消して、提出する媒体の中には残さないようにしておきなさい。
展示写真/会場写真は、内容にも表現にも問題のないもの(見せたいものがきれいに写っている)ものだけを選んで、コメントを添えて、写真フォルダなどに収めておきなさい。
CDなどに記録して提出する場合は、本体とは別の媒体を使いなさい。
提出票の題名欄には "...を媒体とする表現[...]の制作および発表" と記入しなさい。作品の題名をそのまま記入してはいけません。
ビデオならDVテープ、写真ならCD/DVDなどの媒体に記録して提出するのがふつうでしょう。この場合に、提出する作品以外のもの(=ほかの作品や作業の経過)が媒体の中に残っていてはいけません。これらはすべて消して、提出する媒体の中には残さないようにしておきなさい。
展示写真/会場写真は、内容にも表現にも問題のないもの(見せたいものがきれいに写っている)ものだけを選んで、コメントを添えて、写真フォルダなどに収めておきなさい。
CDなどに記録して提出する場合は、本体とは別の媒体を使いなさい。
提出票の題名欄には "...を媒体とする表現[...]の制作および発表" と記入しなさい。作品の題名をそのまま記入してはいけません。
○
・
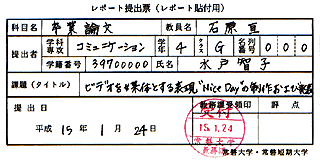
×
・
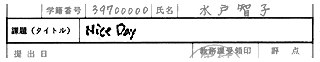
提出票の正しい書き方(上)といけない書き方(下)
提出
| 日時 |
(スクーリングで指示する) |
| 会場 |
卒業制作 ▽ 教務課卒業論文提出窓口 − 進級制作 ▽ 石原研究室 |
必ず、レポート提出票を貼った表紙をケースの巻頭に入れて提出しなさい。
ふつうのレポートの場合は、学生支援センターの窓口で用紙を渡してくれるので、それに氏名などを書いてからレポートの表紙に貼りつけて提出する。
提出された作品ほかは原則として返さません。しかし、作品が手元にないと、あとで自分で発表する場合やポートフォリオに使う場合に困ることになる。だから、写しを作っておいて、そちらの方をを提出し、もとの作品は手元に置いておくようにしなさい。
卒業制作は(ほんとうは進級制作でも)、決められている時刻をほんのちょっとでも遅れたら、絶対に受けつけてはいけないことになっている。
これまでにも実際に、持ち忘れてしまって提出できなくなった場合があった(ほかのゼミだけど)ので、特に気をつけなさい。
Q もしもですが、渋滞なんかのせいで、どうしても決まった時刻までに提出できなくなってしまった場合は、卒業をあきらめるしかないんですか?
A あきらめないで!!!
卒業制作そのものは遅れたりしたら絶対に受け取ってもらえませんが、何分か遅れるぐらいだったら、代わりに、遅れて提出することを特別に認めてもらうための申請書を提出することができます。
ともかく窓口に駆けつけて、申請書の用紙をもらってその場で氏名や間に合わなかった理由などを書いて提出してみましょう。場合によっては特別に遅れて提出することを認めてもらえるかもしれません(審査もあるからあてにはしないでね)。
ゼミによって提出の規則は違っているかもしれません。ほかのゼミの規則と混同して自分が間違えたり、ほかのゼミの学生に間違いを教えて迷惑をかけたりしないように気をつけなさい。
ふつうのレポートの場合は、学生支援センターの窓口で用紙を渡してくれるので、それに氏名などを書いてからレポートの表紙に貼りつけて提出する。
提出された作品ほかは原則として返さません。しかし、作品が手元にないと、あとで自分で発表する場合やポートフォリオに使う場合に困ることになる。だから、写しを作っておいて、そちらの方をを提出し、もとの作品は手元に置いておくようにしなさい。
卒業制作は(ほんとうは進級制作でも)、決められている時刻をほんのちょっとでも遅れたら、絶対に受けつけてはいけないことになっている。
これまでにも実際に、持ち忘れてしまって提出できなくなった場合があった(ほかのゼミだけど)ので、特に気をつけなさい。
Q もしもですが、渋滞なんかのせいで、どうしても決まった時刻までに提出できなくなってしまった場合は、卒業をあきらめるしかないんですか?
A あきらめないで!!!
卒業制作そのものは遅れたりしたら絶対に受け取ってもらえませんが、何分か遅れるぐらいだったら、代わりに、遅れて提出することを特別に認めてもらうための申請書を提出することができます。
ともかく窓口に駆けつけて、申請書の用紙をもらってその場で氏名や間に合わなかった理由などを書いて提出してみましょう。場合によっては特別に遅れて提出することを認めてもらえるかもしれません(審査もあるからあてにはしないでね)。
ゼミによって提出の規則は違っているかもしれません。ほかのゼミの規則と混同して自分が間違えたり、ほかのゼミの学生に間違いを教えて迷惑をかけたりしないように気をつけなさい。
Copyleft(C) 2006-07, by Studio-ID(ISIHARA WATARU). All rights reserved.
最新更新
07-02-12