資料シート●各科目
8mmフィルム
http://www.infonet.co.jp/apt/March/syllabus/bookshelf/8mm.html
8mmは、16mmや35mmおよびその他の同じく、フィルムを使ってムービを制作するシステムの一つだ。70年代から80年代にかけて盛んに使われていたが、最近では、DVなどのビデオによるシステムに役割りを交替している。
8mmは、個人が負担できる範囲の手間と費用でムービが制作できる点に特徴があった。いくつかのバリエーションの中で、シングル8(▽図左)とスーパー8(同右)の2方式が特によく使われていた。この二つは、撮影から現像までの工程については互換性がなく、そのため、カートリッジ、カメラ、現像所についてはそれぞれ専用のものを使い分けなければならなかった。しかし、編集から上映までについては、たがいのシステムを共有することが、ある程度は可能になっていた。
8mmは、個人が負担できる範囲の手間と費用でムービが制作できる点に特徴があった。いくつかのバリエーションの中で、シングル8(▽図左)とスーパー8(同右)の2方式が特によく使われていた。この二つは、撮影から現像までの工程については互換性がなく、そのため、カートリッジ、カメラ、現像所についてはそれぞれ専用のものを使い分けなければならなかった。しかし、編集から上映までについては、たがいのシステムを共有することが、ある程度は可能になっていた。
 |
 |
 |
 |
シングル8(左)とスーパー8のフィルムカートリッジ
厚み方向の構造と機能
8mmに限らずフィルムには裏表がある。横から見て、ざらざらした感じでよく見ると細かい凹凸がある方を膜面(またはエマルジョン面)、つるつるした感じで凹凸がない方を(ふつうは特に名前がないけど)ベース面という。フィルムが反っている場合は、反り方でも裏表を区別できる。内反りになる方が膜面、外反りになる方がベース面だ(▽図)。

膜面(左)とベース面
(極端に描き分けている)
膜面には顔料を糊で練ったものがくっついている。これによって色が記録されている。これをエマルジョンという。カラーフィルムでは、エマルジョンは、感光剤に含まれる塩(しおじゃなくてえん)のうちの感光した部分が現像剤によって金属に変化する時に、現像剤に含まれている(*00)色素基剤が発色および吸着する化学的な作用によって形成される(▽図)。

エマルジョンの形成
エマルジョンを乗せているシートをベースという。ベースはポリエステル(シングル8)やトリアセテート(スーパー8)などでできている。以前はセルロイドが使われていたが、セルロイドは火をつけると爆発のように激しく燃えるので、保存や映写に危険がともなう(映写には強力なランプを使うから)ことが問題になって、新しい素材に切り替わってきた。
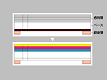
・
フィルムの構造
△
現像前(上)と現像後
上から順にイエロー感光剤/色層、マゼンタ感光剤/色層、シアン感光剤/色層、ベース、ハレーション防止層、磁気録音帯(2本)が順に重なりあってできている
広がり方向の構造と機能
8mmフィルムでは、フィルムの片側(16mmや35mmなどのほかの方式のフィルムでは両側)に穴が開いている。これは、カメラやプロジェクタなどのフィルムに関係があるすべての機械で、フレーム単位でフィルムの走行を制御する(これをパーフォレーションという)のに使う。
膜面を表に向けて、パーフォレーションの穴を右にして、フィルムを縦に置いた状態で、フィルムの上の方向がフレームに写っている像にとっても上、時刻については始めの方になる。逆に、フィルムの下の方向は像の下、時刻では終わりの方になる。この置き方だと、フィルムの内容をつかむのが楽になる。ただし、像の裏表が逆に見えているので、それだけは注意しておく必要がある。
フィルムを横に置く場合は、膜面が表で穴が上なら、フィルムの左の方向がフレームに写っている像にとっては上、時刻については始めの方になる。
膜面を表に向けて、パーフォレーションの穴を右にして、フィルムを縦に置いた状態で、フィルムの上の方向がフレームに写っている像にとっても上、時刻については始めの方になる。逆に、フィルムの下の方向は像の下、時刻では終わりの方になる。この置き方だと、フィルムの内容をつかむのが楽になる。ただし、像の裏表が逆に見えているので、それだけは注意しておく必要がある。
フィルムを横に置く場合は、膜面が表で穴が上なら、フィルムの左の方向がフレームに写っている像にとっては上、時刻については始めの方になる。
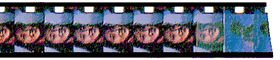
・
8mmフイルム 膜面
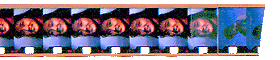
・
8mmフイルム ベース面
△
上から順にサウンド.A、ビデオ、パーフォレーション、サウンド.B(*01)
時間は左から右に向かって流れている
ショットのつなぎ目がスプライシングテープで貼り合わされているのが分かる
*00
サクラカラー(今でもあるんだろうか)やAgfaのフィルムでは感光剤の方に混ぜておく方式が使われていた
*01 実は、シングル8の公式の規格では、パーフォレーションホール側の磁性帯は、正確にはバランストラック(balance track)と呼ばれるべきもので、録音のためのものではない。
もし、このトラックがなくて逆側だけに磁性帯がつけてあると、フィルムの厚みがその分だけ左右で違ってしまう。バランストラックは、それを打ち消してフィルムの面をレンズに対して平行に保つためのあげ底の役割りを果たしている。
ところが、他社はいろいろな拡張を提案して、バランストラックにも録音できるようにすることによってアフレコやステレオなどの機能を実現してしまった。そのために、富士フィルムの製品も、他社のフィルムも上映できるようにという立場から、同等の機能を備えなければならなくなった。
このくい違いは、特別な処理をラボに依頼する場合に問題になる。ラボが備えている機材は、公式の規格にしか対応していない場合があるからだ。たとえば、シングル8からビデオテープへのダビングを依頼する場合、サウンド.Aとサウンド.Bとでステレオを実現していても、左右の音がミキシングされたモノラルのテープしか作れないかもしれない。このような場合は、サウンドの取り扱いについて、前もってラボと打合せをしておいた方がいいだろう。
*01 実は、シングル8の公式の規格では、パーフォレーションホール側の磁性帯は、正確にはバランストラック(balance track)と呼ばれるべきもので、録音のためのものではない。
もし、このトラックがなくて逆側だけに磁性帯がつけてあると、フィルムの厚みがその分だけ左右で違ってしまう。バランストラックは、それを打ち消してフィルムの面をレンズに対して平行に保つためのあげ底の役割りを果たしている。
ところが、他社はいろいろな拡張を提案して、バランストラックにも録音できるようにすることによってアフレコやステレオなどの機能を実現してしまった。そのために、富士フィルムの製品も、他社のフィルムも上映できるようにという立場から、同等の機能を備えなければならなくなった。
このくい違いは、特別な処理をラボに依頼する場合に問題になる。ラボが備えている機材は、公式の規格にしか対応していない場合があるからだ。たとえば、シングル8からビデオテープへのダビングを依頼する場合、サウンド.Aとサウンド.Bとでステレオを実現していても、左右の音がミキシングされたモノラルのテープしか作れないかもしれない。このような場合は、サウンドの取り扱いについて、前もってラボと打合せをしておいた方がいいだろう。
8mmフィルムの編集は、実際にフィルムを切ったり貼り合せたりすることによって行なう。この作業には、エディタ(<editor。またはビュア<viewer)とスプライサ(splicer)を使う
。 フィルムとフィルムとを貼り合せるのには、とても薄くて、パーフォレーションがあらかじめ開けてある専用の粘着テープを使う。このテープをスプライシングテープという。
。 フィルムとフィルムとを貼り合せるのには、とても薄くて、パーフォレーションがあらかじめ開けてある専用の粘着テープを使う。このテープをスプライシングテープという。
参考にした資料
脇リギオ
写真技術ハンドブック
(ダヴィッド社、62-09-30)
Andrew Glassner
"An Open and Shut Case"
IEEE Computer Graphics and Applications
Vol.19, No.3, (99- 05+06) pp.82-92
ほしのあきら
フィルム-メーキング
個人映画制作入門
(フィルムアート社、75-02-20)
・

フジカラーサービス
(私信、01-06-11)
ジャンクション
▽
8mm/16mm
映像
Copyleft(C) 1997-04, by Studio-ID(ISIHARA WATARU). All rights reserved.
最新更新
04-04-06