資料シート●各科目
易
えき yi
http://www.infonet.co.jp/apt/March/syllabus/bookshelf/E/eki.html
易(えき、yi)は古代の実践的な哲学の一つで、周(今の中国)の[易経](えききょう、Yijin)という著作によって現在に伝えられている。
[易経]には64種類の象(しょう)と呼ばれる行動の指針が書かれている。それぞれの象はたがいに矛盾したことを指示しているように見える。このように、易はほかの哲学や宗教とはかなり異なった考え方を基本に置いている。
易では、宇宙は変化を続けていて、いつも同じ唯一の法則で成立しているわけではないと考えている。したがって、個人の生き方や社会のあり方の原則も、それに合せて変化し続けていなければならない。
易に基づいて行動するためには、まず、現在の宇宙の状態がどの象に当たるか調べる必要がある。これには、筮竹を取り分けて偶奇を見るなどの手順が使われる。
易は占いの一つのように誤解されることが多い。しかし、易は占いではない。易を使っても、未知の何かを超常的に知ることができるわけではない。その瞬間にどう行動するべきなのか決めることができるだけだ。
[易経]には64種類の象(しょう)と呼ばれる行動の指針が書かれている。それぞれの象はたがいに矛盾したことを指示しているように見える。このように、易はほかの哲学や宗教とはかなり異なった考え方を基本に置いている。
易では、宇宙は変化を続けていて、いつも同じ唯一の法則で成立しているわけではないと考えている。したがって、個人の生き方や社会のあり方の原則も、それに合せて変化し続けていなければならない。
易に基づいて行動するためには、まず、現在の宇宙の状態がどの象に当たるか調べる必要がある。これには、筮竹を取り分けて偶奇を見るなどの手順が使われる。
易は占いの一つのように誤解されることが多い。しかし、易は占いではない。易を使っても、未知の何かを超常的に知ることができるわけではない。その瞬間にどう行動するべきなのか決めることができるだけだ。
卦
象のそれぞれには符号が対応づけられている(▽図)。この符号は陽(よう、yang)/陰(いん、yin)の2種類の記号を六つ並べたもので、卦(け)と呼ばれている。
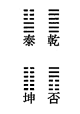
卦を構成する六つの記号が置かれる桁をそれぞれ爻(こう)という。
筮法
易経には64種類の象が書き並べられている。易者は、天地が定めるのに従って(=偶然に)そのうちのどれかを選択し、それにしたがって行動する。
象を選ぶ手順を筮法(ぜいほう)という。易者のくせのために偶然の作用が乱されないように、筮法にはいろんな工夫が折り込まれている。正式な筮法では、50本の筮竹を操作して、とても長い手順を経て象を選ぶ。
日本では略筮法(▽図)も用いられている。
象を選ぶ手順を筮法(ぜいほう)という。易者のくせのために偶然の作用が乱されないように、筮法にはいろんな工夫が折り込まれている。正式な筮法では、50本の筮竹を操作して、とても長い手順を経て象を選ぶ。
日本では略筮法(▽図)も用いられている。
・筮竹から1本を取って机に置く
・残った筮竹を左右の手に分ける。左手の筮竹を天(てん)といい、右手のを地(ち)という
・地から1本を取って左手の小指に挟む。これを人(じん)という
・天から8本ずつ取っては机に置いていく
・取れなくなったら天が何本になったか数える。0〜7本の八つの場合があるが、これらは同じ確率で起こる
・表に従って、天に対応する卦の下半分を求める
・以上と同じ手順をもう一回行なって卦の上半分を求める
・経に従って、卦に対応する象を求める
卦とビットとの類似
陽を×、陰を○に置き換えると、卦は象に割り当てられた6桁のビット列による符号だと見なすことができる。
略筮法の場合は、天に残った筮竹の本数と、卦の半分が表現する自然な整数とが完全に対応している。
陽は偶数(例:0)を、陰は奇数(例:1)を象徴していると考えている人がいるが、ふつうは×は"0"で、○は"1"で書き表わされるので、ここにも一致が見られる。
略筮法の場合は、天に残った筮竹の本数と、卦の半分が表現する自然な整数とが完全に対応している。
陽は偶数(例:0)を、陰は奇数(例:1)を象徴していると考えている人がいるが、ふつうは×は"0"で、○は"1"で書き表わされるので、ここにも一致が見られる。
戦略としての易
ゲーム(=試合、企業の競争、戦争、...)が何回も繰り返される場合、一つだけの戦術(例:必ずグーを出す)では絶対に負けてしまうような状況でも、複数の戦術を取り混ぜて使う(例:グー/チョキ/パーを同じ割合いで出す)ことによって、負けを最小限に押えることができることが知られている。このようなゲームの戦い方を混合戦略という。
現代の見方からすると、易は、混合戦略の技術と見なすことができる。易は、現代でも通用する合理的な根拠(それはもともと経験的なものだったかもしれないけど)をもった、きちんとした技術なのだ。
Q:
偶然に戦術が選ばれるようにするより、自分がこれまでにとってきた戦術を記録しておいて、その傾向をわざと外すように戦術を選ぶようにした方がいいんじゃないですか?
A: いい方法に気がつきましたね。でもそれではうまくいきません。
相手が自然ならいい(たぶん)んですが、考えて判断ができる人間や組織が相手だと、これまでの傾向をわざと外すように戦術を選ぶことも、最初から予想されてしまっていると考えなくてはいけません。
相手の裏の裏の裏をかくためには、いつも外すのではなくて、場合によって外したり外さなかったり(=決まった傾向のとおりにする)して、撹乱する必要があります。その選択は、やはり偶然にしたがって行なわなければなりません。
この考え方は、LANでも使われています。イーサネットという手法のLANでは、サーバからトークンという手形のようなものを割り振ってもらって、それを情報にくっつけて送り出します。でも、たまたま同時に二つのコンピュータがトークンをもらいに行って、鉢合わせしてしまうことがあります。そんな場合には出直してもらいますが、ふつうに出て行ったら、コンピュータは正確ですから絶対にまた鉢合わせをしてしまいます。そこで、偶然にしたがって早く出るか遅く出るかを決めるようにしています。
現代の見方からすると、易は、混合戦略の技術と見なすことができる。易は、現代でも通用する合理的な根拠(それはもともと経験的なものだったかもしれないけど)をもった、きちんとした技術なのだ。
Q:
偶然に戦術が選ばれるようにするより、自分がこれまでにとってきた戦術を記録しておいて、その傾向をわざと外すように戦術を選ぶようにした方がいいんじゃないですか?
A: いい方法に気がつきましたね。でもそれではうまくいきません。
相手が自然ならいい(たぶん)んですが、考えて判断ができる人間や組織が相手だと、これまでの傾向をわざと外すように戦術を選ぶことも、最初から予想されてしまっていると考えなくてはいけません。
相手の裏の裏の裏をかくためには、いつも外すのではなくて、場合によって外したり外さなかったり(=決まった傾向のとおりにする)して、撹乱する必要があります。その選択は、やはり偶然にしたがって行なわなければなりません。
この考え方は、LANでも使われています。イーサネットという手法のLANでは、サーバからトークンという手形のようなものを割り振ってもらって、それを情報にくっつけて送り出します。でも、たまたま同時に二つのコンピュータがトークンをもらいに行って、鉢合わせしてしまうことがあります。そんな場合には出直してもらいますが、ふつうに出て行ったら、コンピュータは正確ですから絶対にまた鉢合わせをしてしまいます。そこで、偶然にしたがって早く出るか遅く出るかを決めるようにしています。
参考文献
・
金谷治
講談社現代新書 303
易の話
(講談社、72-12-28)
このページの記事の一部は 媒体への負荷や著作権への配慮から バージョンによっては見ていただけないことがあります
Copyleft(C) 2000-06, by Studio-ID(ISIHARA WATARU). All rights reserved.
最新更新
06-05-26