資料シート●各科目
マゼンタ
magenta
http://www.infonet.co.jp/apt/March/syllabus/bookshelf/magenta.html
色の一つ。

日本では、唐紅(からくれない)と呼ばれていた色がマゼンタに当たる。
マゼンタのような紫系の色は、自然の素材には見い出すことが難しい(空の色として認識されるようになったが空は持って来られない)ために、多くの時代、地域で高貴な色として扱われていた。そこで、近代になって有機物の合成の技術が確立すると、紫系の顔料/染料の合成が試みられるようになった。
まずモーブが初めての合成染料として合成され、続いて1859年にフクシン(fuchsine。▽図)という染料が発明された。これらの成果によって、紫はより安価に使える色になった。
マゼンタのような紫系の色は、自然の素材には見い出すことが難しい(空の色として認識されるようになったが空は持って来られない)ために、多くの時代、地域で高貴な色として扱われていた。そこで、近代になって有機物の合成の技術が確立すると、紫系の顔料/染料の合成が試みられるようになった。
まずモーブが初めての合成染料として合成され、続いて1859年にフクシン(fuchsine。▽図)という染料が発明された。これらの成果によって、紫はより安価に使える色になった。
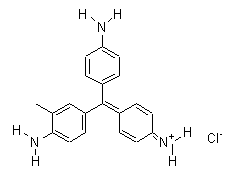
フクシンは分子式がC20H20Cl N3で、アニリンやトルイジン(コールタールに含まれる)から合成され、水やアルコールに溶かすと赤寄りの紫の色を現す。この色はフクシア(Fuchsia)という紫の花を連想させたので、それにちなんで名前がつけられた。また、その色はマゼンタと呼ばれ、それが現在に至っている。
ほとんどすべての種類の繊維を染めることが可能で、生物学の研究では組織の染色に使われている。
マゼンタという名前は、実はイタリア北部の都市 Magenta(マジェンタ)に由来する。
Versalle時代よりも前からイタリアはいくつもの小国に分裂していたが、その統一を妨げている理由の一つは、北部をオーストリアが支配していることにあった。そこで、1859年にサルディニアのEmanuele 2世(エマヌエレ-、Vittorio)は、フランスのNapoleon 3世と同盟(この時にサボイとニースがイタリアからフランスに譲り渡された)して北部に進軍し、Magentaでオーストリアを敗退させ、Milano(▽図) を解放した。
ほとんどすべての種類の繊維を染めることが可能で、生物学の研究では組織の染色に使われている。
マゼンタという名前は、実はイタリア北部の都市 Magenta(マジェンタ)に由来する。
Versalle時代よりも前からイタリアはいくつもの小国に分裂していたが、その統一を妨げている理由の一つは、北部をオーストリアが支配していることにあった。そこで、1859年にサルディニアのEmanuele 2世(エマヌエレ-、Vittorio)は、フランスのNapoleon 3世と同盟(この時にサボイとニースがイタリアからフランスに譲り渡された)して北部に進軍し、Magentaでオーストリアを敗退させ、Milano(▽図) を解放した。

フクシンはこの戦闘の直後に発見されたので、1860年からその色がマゼンタと呼ばれるようになった。イタリアでは、Magentaに続いて激戦が行なわれたSolferinoにちなんでソルフェリーノとも呼んでいる。
MagentaとSolferinoの勝利がきっかけになって、シチリア(当時はナポリ領)のGaribaldi(ガリバルディ, Giuseppe)たちが活躍するイタリア統一戦争が始まり、のちの1861年にはイタリア国民会議が開かれて、ほぼ現在と同じ姿のイタリアが誕生することになる。
MagentaとSolferinoの勝利がきっかけになって、シチリア(当時はナポリ領)のGaribaldi(ガリバルディ, Giuseppe)たちが活躍するイタリア統一戦争が始まり、のちの1861年にはイタリア国民会議が開かれて、ほぼ現在と同じ姿のイタリアが誕生することになる。
参考にさせていただいた資料
福田邦夫
赤橙黄緑青藍紫
(青娥書房) 1979-06-01
福田邦夫
ヨーロッパの伝統色
(読売新聞社) 1988-10-25
Fuchsia.JP
Fuchsine, Magenta, Fuchsia
2002〜2005
羽田明、中山治一、豊田尭
解明世界史
(文英堂)
このページの記事の一部は 媒体への負荷や著作権への配慮から バージョンによっては見ていただけないことがあります
Copyleft(C) 2005, by Studio-ID(ISIHARA WATARU). All rights reserved.
最新更新
05-05-14